■最終更新日:2025.12.4
スマート農業は難しくない!家庭菜園にも導入できる神アプリや便利ツールを紹介
近年「スマート農業」という言葉が、農家以外の方にも少しずつ浸透してきています。
スマート農業とは平たく言ってしまえば「デジタル技術を活用した農業の総称」です。AI(人工知能)やデジタル技術と言うと少し身構えてしまいそうですが、決して難しいものではありません。それどころか家庭菜園のような、ごく小規模の作物栽培にも導入できるスマート農業がいくつもあります。
本記事では、そんな家庭菜園にも使えるスマート農業について、筆者の主観を交えながら、分かりやすくご紹介していきたいと思います。
本記事を読んで「スマート農業って思ったより簡単そうだ」と、一人でも多くの方に感じていただけたらと思います。

スマート農業とは?
スマート農業を正しく説明しようとすると「ICT・IoT・AIなどの先端技術を活用して、農作業を効率化・省力化・高品質化する新しい農業のこと」だそうです。
いきなり小難しいことを言い出しましたね…
たとえば、センサーで土壌の状態を自動計測したり、オートロボットが自動で田畑を耕したり、AIが作物の生育状況を分析したり。
これにより、経験や勘に頼らずデータに基づいた判断が可能になり、少ない人手でも安定した収量と品質を保つことができます。高齢化や人手不足といった課題を解決し、持続可能な農業を実現する取り組みとして注目されています。
(IcTやIoTなどの専門用語については、本記事の最後にまとめて紹介させていただきます!)

スマート農業は全知全能の存在ではない!
上記なことを言うと、スマート農業ではAIが全てを解決してくれて、全てが自動で行われて…のように、まるで全知全能の神様のような、夢の農業に感じてしまうかも知れません。
そして、ものすごくハードルの高い農業の方法のように感じてしまうのではないでしょうか?
しかし実際にはそんなことはありません。遠い未来のことは分かりませんが、少なくても現時点ではあくまで人間の農業を支えるための技術や仕組みであって、万能ではないし、すべての課題を自動的に解決してくれるものでもありません。
ましてや全自動で勝手に作物を作り収穫してくれるような、22世紀の某タヌキ型ロボット「ドラ〇もん」のような話ではないのです。
2025年現在のスマート農業は、あくまで人を補助するために存在しているものなのです。

■スマート農業の強み
・データに基づいた判断ができる(気象・土壌・作物の状態など)
・労働負担を軽減できる(自動運転トラクター、ドローン散布など)
・精密な栽培管理が可能(必要な分だけ肥料や水を与える)
・遠隔監視や記録の自動化によって経営改善に役立つ
■スマート農業の弱み
・導入コストが高い:機器やシステムが高額で、中小農家には負担。
・データや機器の扱いに知識が必要:ITリテラシーやメンテナンスが不可欠。
・自然環境の変動は完全には制御できない:異常気象や予期しない害虫などには限界がある。
家庭菜園でもできるスマート農業
あれこれ言っても結局スマート農業は導入するのにお金もかかって大規模農場向けのものなんでしょ?と思われてしまうかと思います。そもそも家庭菜園レベルでAIなんて導入する必要ないし…と考えられる皆さん。スマート農業とはそんなにとっつきにくいものではないのです。
冒頭にも書きましたが、スマート農業は簡単に言えば「デジタル技術を活用した農業の総称」です。
そしてもっと早い話をすると、皆さんがお持ちのスマートフォンなどを使うことで、簡単にスマート農業を行うことができます。
ここからは家庭菜園でもできるスマート農業について紹介していきたいと思います。
■アプリで病害をチェック!「PictureThis」
作物の健康状態を判定できる神アプリがあります。家庭菜園の1つのネック、それは作物の病気だと思います。作物に異変が起こっても病害の特定というのは知識がないとなかなか難しいものです。
病気が分からないと対処の仕方もわからず、その時点で作物の育成を諦めてしまうかも知れません。
そんな時スマートフォンアプリ「PictureThis」を使えば、スマートフォンのカメラ機能で作物を撮影するだけで、健康状態の判定、病害の特定を行うことができます。
基本的には野草を撮影するとその植物が何かを教えてくれるアプリで、有毒植物の判定などにも役立てることができます。本アプリの優秀さは、120万以上の★5レビュー(平均★4.8)と1億を超えるダウンロード数が物語っています。
「PictureThis」を使うことでAIの力で作物の健康管理を行うというスマート農業を実現することができます。

■土に差すだけで状態チェック!「土壌テスター」
家庭菜園を行う際に「土の栄養は足りてるか?」「水やりの量はあっているか?」が気になることはありませんか?そんな時、土に差すだけで土壌の栄養状態や水分量、Ph値やさらには日光量などを測定してくれるのが土壌テスターです。
つまり土壌テスターを使うことで、土に不足している、または過剰となっている要素を知り、育てる作物に合わせ最適な土の状態を作り上げることができるというわけです。
土壌テスターは本当に土に差すだけのため使い方は非常に簡単。もちろん鉢やプランターでも使用することができます。
土壌テスター自体は30~40年以上前からあると言われていますが、近年はWi-Fiを使いスマホアプリと連携し詳細な数値と、そのログをとれるタイプのものが登場しています。
現在アプリ側の日本語対応が見つからず、実装が待たれるところではあります。ただパラメータを読むだけなため簡単な英単語の意味さえわかれば、そこまで不便はありません。

■旅行中の水やりにも!「自動散水機」
家庭菜園をはじめると、旅行などで数日間家をあけるときなど「水やり」をどうしよう?と考えてしまいます。また長期外出がなくても、忙しい日常の最中、水やりを忘れてしまったというケースは起こりがちです。特に近年は、地球温暖化の影響もあり水やりの重要性も増してきています。
そんな時非常に便利なのが自動散水機です。
時間や水量を予め設定しておくことで、自動で作物への水やりを行ってくれるのが自動散水機です。散水と言うと水をばらまくイメージですが、複数のノズルがあり鉢ごとなど、細かな水やりも可能です。
自動散水機は様々なメーカーから販売されており、値段も「ピンキリ」と言える状態です。水やりの方法(鉢植え対応)や太陽光によるソーラー充電も標準対応となり甲乙つけがたいのですが、個人的にはUSB充電が可能で屋内設置にも強みをもつ、以下の散水機がオススメです。
スマート農業に使われる主な技術
それでは、途中説明を省いた「スマート農業とはうんたらかんたら」に出てくる英語の用語について説明したいと思います。
「IoT」や「ICT」といった、小難しい言葉がでてきますが、これらは特にスマート農業独自の言葉ではありませんので、来たるべきAI全盛時代に備えこの機会に覚えておくのも悪くないかも知れません。
いや、正直こんなもの覚える必要があるのかと疑問にはなります。何となくのイメージができればそれでよいのではないでしょうか?
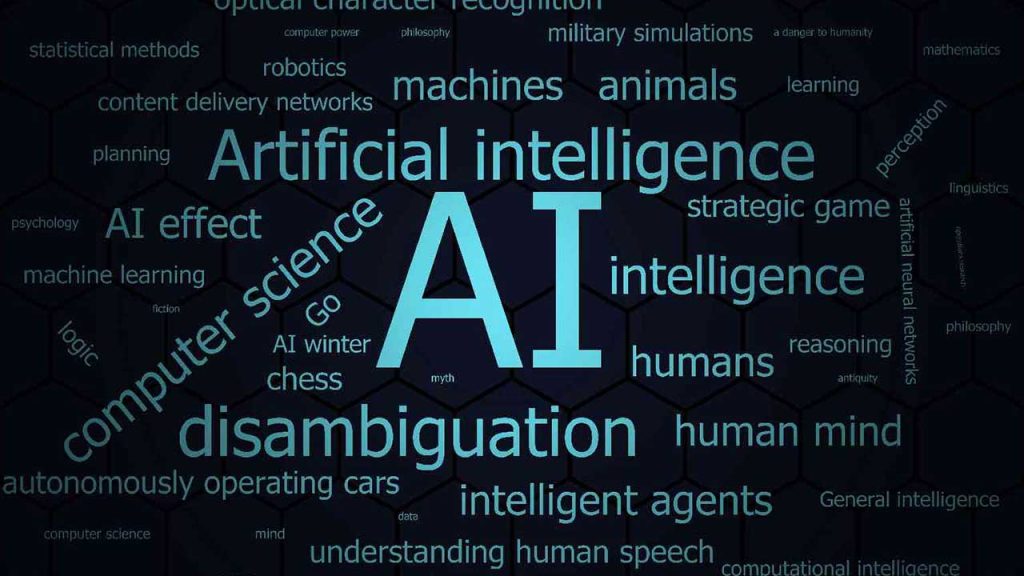
■IoT(Internet of Things)
IoTは「Internet of Things」の略で、日本語では「モノのインターネット」を意味します。
書いてはみたものの、何の略かなんて覚える必要は全くありません。読み方はそのまま「アイ・オー・ティー」です。
意味もとても簡単で、身の回りのものをインターネットに接続し使われる技術のことです。
もし温度計がインターネットにつながっていたら、どこにいてもスマホで温度を確認できるよね?というだけの話です。もちろん双方向の通信が可能なので、温度計側に指示を出すこともできます。
家電などでの具体例として、「外でもスマホから電源をいれられるエアコン」のようなものがあげられます。
■ICT(Information and Communication Technology)
ICTは「Information and Communication Technology」の略で、日本語では「情報通信技術」を意味します。こんな長い名前、もちろん覚える必要はありません。「アイ・シー・ティー」と言っておけばOKです。
名称こそ長いですが、言っていることはとても単純でインターネットを使った情報通信、つまりメールやSNS、それに加え複数人がアクセスできるクラウドサービスなどを指します。
もし日常的にメールやSNSを使っているのであれば、十分に「ICTを使用している」と言えます。
ICTってメールとかSNSのことでしょ?と言われてそれを否定できる人はいません。
■AI(Artificial Intelligence)
AIは「Artificial Intelligence」の略で、日本語では「人工知能」を意味します。ご存知の通り読み方は「エー・アイ」です。Artifical=人工の…ですが、そんなことは忘れましょう。
コンピュータにルールやパターンを学習させることで問題を解決する技術を意味します。
「こういう時どうする?の答えを大量にコンピュータが覚えてくれる」という認識で問題ないと思います。
身近なところでは、スマホのロック解除などにも使われる顔認証や指紋認証がAI技術としてあげられます。これは「この顔の時はロックを解除する」というパターンをコンピュータに覚えさせたということになります。この他では車の自動運転機能などが身近なAI技術の例として挙げられるでしょうか?
| 技術 | 内容 | 例 |
|---|---|---|
| IoT(モノのインターネット) | センサーや機器がデータを自動収集・送信 | 土壌センサー、気象観測装置 |
| ICT(情報通信技術) | データをネットワークで共有・分析 | クラウド型農業日誌 |
| AI(人工知能) | データを学習して判断や予測を行う | 病害虫診断、収量予測、画像分析 |
皆さんは既にスマート農業の入口に立っている!
いかがでしたでしょうか?
スマート農業という言葉は耳にしたことがあっても、それについて考える機会と言うのはなかなかなかったと思います。AIの活用やデジタル技術などと言われると、とても敷居の高い技術に感じてしまいますが、実際にはそんなことはありません。
少なくとも今この記事を読んで下さっている皆さんなら、確実にスマート農業を行うことができると断言することができます。そう言える理由について最後に説明させてください。
■既にAIを活用している
おそらく多くの皆さんが、GoogleやYahoo!の検索機能からこの記事に辿りつかれたのではないでしょうか?
この「GoogleやYahoo!の検索機能」ですが、実は「AI」が皆さんの求めているであろう内容を学習し、検索したキーワードに合わせて条件にあったサイトを表示しています。
皆さんが何かを知ろうと検索窓に言葉を入力した時、既に皆さんはAIを使いこなしており、必要な情報を入手することができているのです。
■ICTだって活用している
次に皆さんはAIだけではなく「ICT」も活用できていると言えます。
ICTとは情報通信技術です。ものすごく簡単に言えば、インターネット通信を使って情報を入手する技術と言えます。
今皆さんは、インターネットを使ってこのページを読んでいます。そう言える理由は、この記事がインターネット上に置かれているからです。逆にインターネットに接続せずにこの記事を読むことはできません。それはこの記事を書いている私ですら、です。
この瞬間、皆さんはインターネットという通信技術を使い情報を得ています。これは皆さんがひとつのICTを使いこなしている、そう言うことができるのです。

つまり本記事を読んで下さった皆さんは「すでにスマート農業」を行っている、そう言っても何も間違いではないのです。本記事を読んで「スマート農業って思ったより簡単そうだ」と一人でも多くの方に感じていただけたら幸いです。
東京戸張株式会社のWEB担当。
兼業農家に生まれ、家庭菜園と米づくりの経験は20年近くとなる。
副業でミミズを育て売るというかなり特殊な父親に育てられた。
土いじりもパソコンいじりも好き。だが、この世界で最も嫌いなものはきゅうり。


![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4de1fd82.036f8680.4de1fd83.c6bc6136/?me_id=1390050&item_id=10000564&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fshunkado-shop%2Fcabinet%2Fmizuyariki%2F10672743%2Fimgrc0082482656.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)




























