■最終更新日:2025.7.31
【5分でわかる】草おさえ。雑草対策の新しい選択肢!防草シートとの違いは?
広範囲の雑草を抑制したい場合に防草シートが多く用いられてきましたが、近年では草おさえを使用するケースが非常に増えてきました。
草おさえ(草抑え)の使用する具体的な目的として、単に「草が生えないようにする」だけでなく、安全・美観・維持管理・環境保全といった幅広い理由があります。
本記事では新しい雑草対策として普及の進む「草おさえ」について、簡潔に紹介して行きます。
※本記事は5分での可読文字数とされる1,500~2,000文字を目安に書かれています。

草おさえとは?
草おさえは、その名の通り「草をおさえるためのネット(シート)」です。地面に敷設することでシート化の雑草を「おさえ」ます。
使用する最大の目的は、防草シートと同じく雑草の繁茂を防ぐことにあります。雑草が生い茂ると景観が悪くなるというだけでなく、定期的な草刈りや除草作業が必要になります。
草おさえを使うことで、これらのメンテナンス回数やそれにかかるコストを削減することができます。
特に夏の猛暑下での広範囲の草刈りは熱中症のリスクを大きく高めてしまいます。

草おさえの特長(防草シートとの違い)
ここまで聞くと、防草シートと何が違うの?という感想を持たれる方も多いと思います。防草シートとの差について具体的に紹介したいと思います。
■防草シートとの違い
草おさえと防草シートの最大の違いは「光を通すか通さないか」にあります。
草おさえは半透明であるため光を通し、防草シートは光を通しません。この差はシート下の雑草が光合成できるかできないの差となり、光を遮断する防草シートの場合では雑草は光合成を阻害され、栄養分(糖)を作ることができないため、じきに枯れて行きます。
普通に考えれば雑草は枯れた方が良いと感じますが、一概にそうは言えません。雑草の根は土壌を掴み支えているからです。
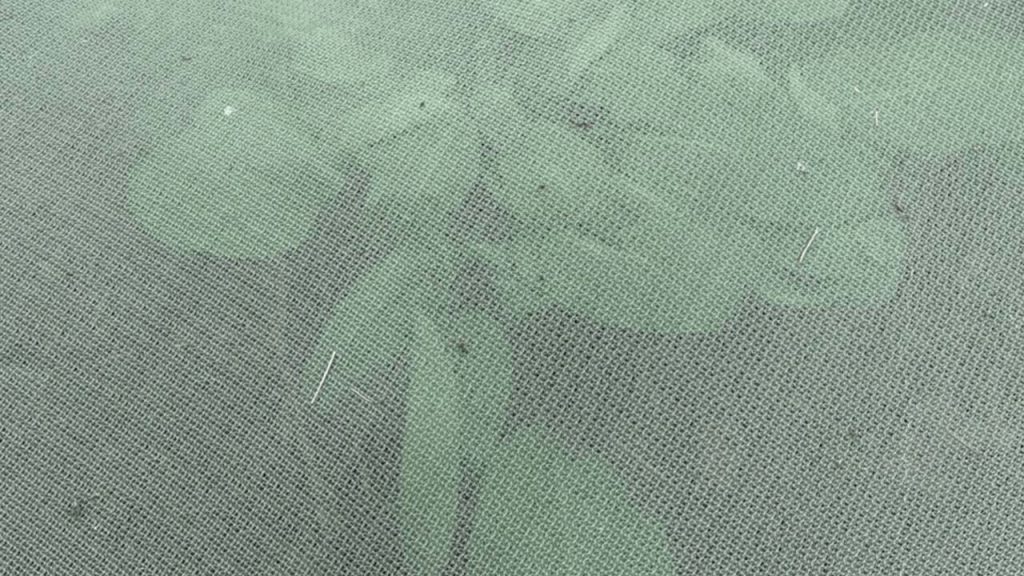
■草おさえの特長
草おさえは前述の通り、雑草を抑えながらも光をある程度通すことで、雑草を枯らさずに雑草の力で土壌を守ることができます。このような理由から、斜面や土が緩い場所などの土壌流出が懸念される場所での使用に草おさえは向いています。
さらには草おさえは高密度の生地でないため、重量が軽いうえに柔軟性・伸縮性が高く、作業性に非常に優れています。防草シートより持ち運びがラクで、敷設も簡単だと言えます。
■景観の保護にも最適
草おさえは自然になじむ「景観色(緑色)」であることも大きな特長であると言えます。
防草シートの場合は光を完全に遮る必要があることから、どうしても黒かそれに近しい暗い色の生地になってしまいます。
この理由から、公園など景観を保つ必要のあるエリアでの草おさえの需要が非常に高まっています。

草おさえと防草シートとの住み分け
草おさえと防草シートとの住み分けはどのように考えるべきなのでしょう?以下の点に
■草おさえが適している場所
草おさえが適している環境は大きく二つです。ひとつは「土壌を保護したい場合」、もう一つは「景観を壊したくない場合」です。
【草おさえが適した場所】
・土壌を保護:土壌の緩い斜面や法面など
・景観を維持:公園や庭、芝生などの下に枯らしたくない植物がある場合
■防草シートが適している場所
防草シートは「絶対に草を生やさない場合」に使うべきだと言えます。
【草おさえが適した場所】
・駐車場や歩道、雑草を抑制したい耕作地など
※特にシートの上に砂利を敷く場合は必ず防草シートを使用しましょう。

木に住み着く害虫の対策にも
草おさえを紹介する上でもう一つ欠かせないのが、樹木に住み着く害虫の対策としての使用方法です。
これらの害虫の中でも多くの都道府県より注意喚起が促され、特に危険視されているのが特定外来生物である「クビアカツヤカミキリ」です。
もしクビアカツヤカミキリを発見した際には確実に駆除し、他の樹木へ被害がひろがらないよう、クビアカツヤカミキリが発見された樹木を網で覆う(網巻)必要があります。この時に樹木に巻き付ける網として、草おさえは目が細かく十分な強度を誇るため最適なのです。


駆け足での説明でしたが、雑草のもう一つの対策「草おさえ」の魅力について伝わりましたでしょうか?さらに詳しく草おさえについて知りたい方は、以下の記事で丁寧に紹介していますので是非参考にしていただければと思います!
農業資材のプロとして、防鳥網や防風ネットなどの製品販売、施工、
その後のサポートまでワンストップで手掛けています。
現場でのさまざまな経験を基に、皆様の役に立つ情報を発信していきます。




























