■最終更新日:2025.12.5
【GW企画】朝の果物は金!果物は朝食べるべき?ウソ?ホント?
ゴールデンウィーク(黄金週間)は、もともと映画業界の売上が、5月の連休中が非常に好調だったことから命名された言葉です。
本ブログは「農業ブログ」と題していますが、黄金週間にちなみ何か農作物にまつわる「金(きん)」の話をお伝えできればと考えた結果、「朝の果物は金」という格言についてその真偽を確かめたい!と思い立ちました。
果物は朝食べることで金の効果が得られるのか?それに対する反論は?本記事で紹介して行きたいと思います。

朝の果物は金とは?
「朝の果物は金」。この言葉は「昼は銀、夜は銅」と続きます。
果物は朝食べることで最も良い効果が得られ、昼になると少し価値が下がり、夜に食べると最も効果が得られない。結局「果物は朝食べるのが一番いいよ」という言葉です。
朝食は、朝、昼、夜それぞれの食事の間隔を比較すると最も時間のあいた食事ということもあり、身体の反応も大きく、重要視されているということが、この「朝の果物は金」の重要な要素だと思います。

朝の果物は金、その出所は?
■果物ってリンゴのこと?
まずは誰が言い始めた問題ですが、出展を探っていくと海外に端を発しています。
どうやらこの言葉は、ヨーロッパ(イギリスともスペインとも)のことわざ「Fruit is gold in the morning, silver at noon, and lead at night.」を和訳したもののようです。
この言葉をさらに調べていくと、一部では「An apple is gold in the morning, silver at noon, and lead at night.」のように書かれており、果物とはリンゴを意味していたことが分かります。

そういえば過去きゅうりについて言及した記事「キュウリの魅力と人気の秘密!」の中でも、英語原文の中で、きゅうりは「Fruit」として記載されていました。「Fruit」とはかなり広義で使われる言葉のようです。
【関連記事】キュウリの魅力と人気の秘密!育成も簡単、家庭菜園にもオススメ!
https://tokyotobari.co.jp/tobari-net/2025/01/21/post-558/
■果物ってバターのこと?
さらに調査を進めると、1721年出版のジェームズ・ケリー著『スコットランドのことわざ大全』の中に「Butter is gold in the morning, silver at noon, and lead at night.」という一文を発見しました。
え?バター?果物でもなく乳製品??さらにケリーの文章は次のように続きます。「よく聞く言い回しだが、その真偽や理由について私は何も知らない。」
リンゴが先かバターが先かは分かりませんが、この本が書かれた1721年では、すでによく聞く言い回しとして存在していたようです。そして根拠はわからない…

【参考】Googleブックス:「A Complete Collection of Scotish Proverbs」
https://books.google.co.jp/books?id=BEgOAAAAQAAJ&redir_esc=y
■1721年の世界と日本
ジェームズ・ケリーが「朝のバターは金」を紹介した1721年は日本で言えば江戸時代、8代将軍徳川吉宗の時代です。世界的に見ても、アメリカはまだ独立しておらず、フランスは革命前のルイ15世の統治、まだ魔女狩りも行われていました。
この時代の言葉であるなら「朝のバターは金」に科学的な根拠があったとは思えません。ただひとつ想像できるのは、冷蔵庫の無い時代です。(冷蔵庫の発明は1803年)。時間経過とともに質が落ちていくことからも「朝のバターは金」と言われるのは分かる気がします。加工技術があがった現在でもバターの常温保存での賞味期限は1~2日とされています。
リンゴが先かバターが先かわからないと書きましたが、やはり「朝のバターは金」が先にあり、そのオマージュとして「朝のリンゴ(果物)は金」が生まれたと考えるべきだと思います。理由は先述した通り、冷蔵庫の無い時代に存在していた言葉のため、バターは夜には劣化していたと推測されるためです。リンゴは常温でも朝晩でそこまでの劣化があったとは考えにくいです。
朝の果物は金なのか?良いとされる理由
「朝のバターは金」が先にあり、そのオマージュで「朝のリンゴ(果物)は金」が生まれたと考えると、朝のリンゴが体に良いことには根拠があると考えられます。すでに大衆に浸透している言葉をもじってリンゴの魅力をPRしたと考えられるからです。
■栄養素の補給に最適
朝の果物が金とされる一番の理由は、やはり「栄養素の補給」です。特に糖を補給し、睡眠時に消耗したエネルギーを効率良く補給できるという点が大きく優れています。どんな食品でもある程度の糖の補給はできるのですが、果物に含まれる「果糖」は消化が早くエネルギーに変換されやすいため、朝食に適していると考えられています。
さらには果物はビタミンやミネラル、食物繊維が豊富なため、一日の活動に必要な多くの栄養素を同時に補給できる点や、体内の水分補給にもつながり身体をスムーズに活動させるとされています。

■脳のエネルギー源「ブドウ糖」
人間の脳というのは大量のエネルギーを消費します。実は寝ている間にもそのエネルギーは消費され続けています。脳の重量は体全体で考えるとわずか2%ですが、体全体のエネルギーのなんと18%をも脳が消費しています。
脳が最も効率的に利用できるエネルギー源は「ブドウ糖(グルコース)」で、このブドウ糖を多く含むことも果物は朝食に適しているとされる理由のひとつです。脳はブドウ糖を蓄えることができず、食事として定期的に摂取する必要があります。
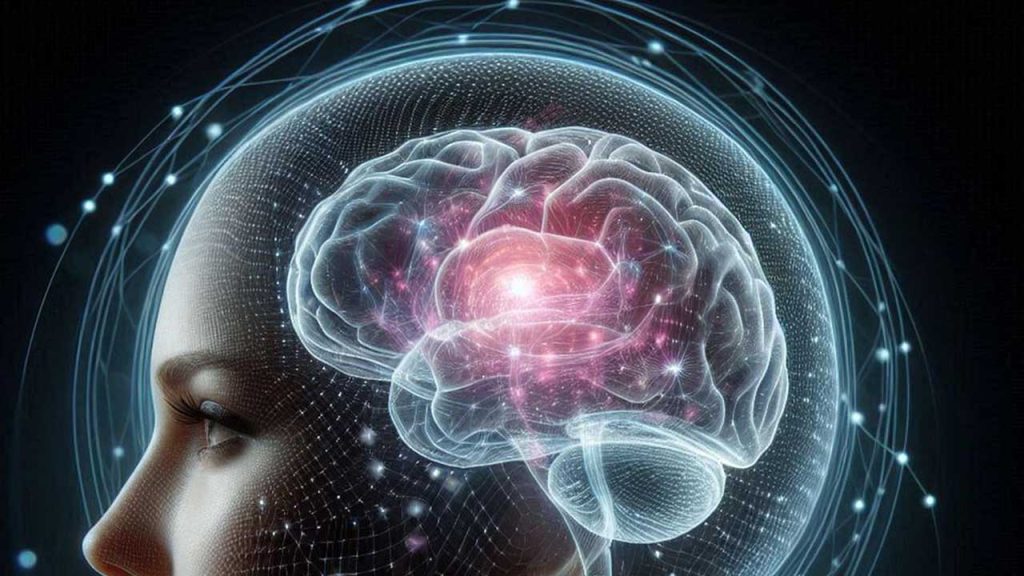
■消化を助け腸内環境を改善!
もちろん果物は多くの食物繊維を含みますが、それだけではなく果物は多くの「酵素」を含みます。
「酵素」は食べ物を分解・消化したり、細胞の修復なども行う非常に人体にとって重要な物質です。
例をあげるとパイナップルに含まれる「ブロメライン」や、キウイフルーツに含まれる「アクチニジン」はタンパク質を分解する酵素であり、胃の中でアミノ酸へと分解することで消化を助けます。
酵素は果物だけでなく野菜にも含まれることも多いのですが、熱に弱く、生で食べることが多い果物の方が効率的に吸収できるのです。
朝に果物を食べることで、不要物排出を促すことができるのです。

朝、果物を食べることで生じる危険も?
■体を急激に冷やしてしまう
「朝の果物は金ではない」とされる理由のひとつは、フルーツには「身体を冷やす」効果をもつものが多いことです。体温の低下は、血流の悪化や免疫力の低下、代謝が悪くなり老廃物をため込んでしまう=太りやすくなってしまうなどの懸念があります。もちろん果物自体は他の食品に比べカロリーや脂質も低いため果物だけを食べる分には大きな問題はありませんが、他との組み合わせで、という話にはなります。
このように体を冷やす食べ物は、漢方医学において「陰性食品」と呼ばれています。陰性食品としてあげられる果物は、柿、バナナ、マンゴー、スイカ、パイナップルなど。特に暖かい地域で育つ果物には陰性食品が多いのです。
一方で果物の中には身体を温める働きを持つ「陽性食品」もあり、リンゴ、さくらんぼ、ブドウなどが該当します。

■光毒性物質ソラレン
柑橘類の一部は多くのソラレンを持つことで知られています。ソラレンは「光毒性」の物質で、紫外線への肌の反応を高め、日焼けやシミを起こしやすくする物質です。
こう聞くと非常に怖い物質ではありますが、キウイフルーツやオレンジなどの多くの果物はほぼ無視できる程度の量しか含有されておらず、風評被害の面が強いとされています。
しかし一方で「グレープフルーツ」や、野菜ですが「パセリ」はソラレンの含有が多く、グレープフルーツジュースなど一気に多くの量を摂取できる食品については注意が必要です。
駒沢女子大学の調査によると、グレープフルーツで日焼けの増す可能性がある摂取量はおよそ457g、ジュースの場合は1リットル以上。これでもかなり安全な試算のようで普通の食事の中で摂取するのはかなり難しいと言えるでしょう。

【参考】駒沢女子大学:「果物や野菜に含まれるソラレンの量はどのくらい?」
https://www.komajo.ac.jp/uni/window/healthy/he_diary_teacher_20002.html
適量を守ることが最も大切
多くの文献や情報を集めても「結局、果物は朝に食べた方がいいの?食べない方がいいの?」と、明確な答えに行きつくことはできませんでした。例えば身体を冷やす陰性食品ひとつをとっても「陰性食品は別に果物だけではない」「影響がでるほどの量を摂取することがそもそも難しい」など議論の余地が非常に大きく、「朝がダメなら昼や夜ならいいの?」に対しても確定的な答えがやはり存在していないのです。
結論としてあげるのであれば「食べるタイミングよりも適量を食べることが大切」という一言に尽きると思います。例えば栄養価が高いことで知られるブルーベリーも、食べ過ぎると消化不良や、腹痛、便秘や下痢などを引き起こします。
果物に限らず言えば普段吸っている酸素がまさに代表例で、酸素の過剰摂取は酸素中毒を引き起こす可能性もあります。とは言っても、普通に生活する上で酸素中毒になるということは考えづらいでしょう。果物に関しても基本は同じだと思います。
農林水産省の「食事バランスガイド」では果物摂取の目標量は一日あたり200g程度とされています。賛否が定まらない朝、昼、夜のタイミングにとらわれるより、適量を意識することが、健康や美容に結びつきやすいのではないかと思います。
東京戸張株式会社のWEB担当。
兼業農家に生まれ、家庭菜園と米づくりの経験は20年近くとなる。
副業でミミズを育て売るというかなり特殊な父親に育てられた。
土いじりもパソコンいじりも好き。だが、この世界で最も嫌いなものはきゅうり。






























